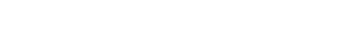AI OverviewsとAI Modeはどう違う?
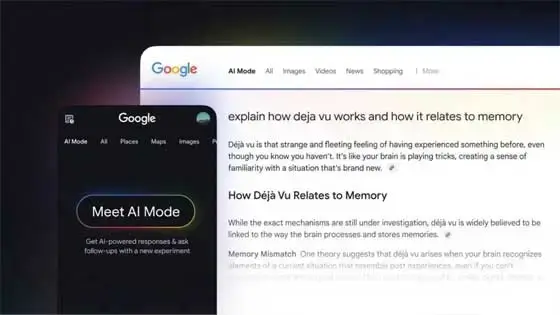 2025年5月20日に開催されたGoogle社の年次技術イベント「Google I/O(アイオー)」で、グーグルCEO(最高経営責任者)のスンダー・ピチャイ氏は、全く新しい検索体験として「AI Mode」を発表しました。
2025年5月20日に開催されたGoogle社の年次技術イベント「Google I/O(アイオー)」で、グーグルCEO(最高経営責任者)のスンダー・ピチャイ氏は、全く新しい検索体験として「AI Mode」を発表しました。
AI Modeは従来のキーワード検索とは一線を画し対話形式で回答を生成します。まずは米国、インドの一部のユーザーを対象に順次提供が始まっているようです。残念ながら日本では2025年8月現在未提供ですが、それほど遠くない将来に日本でも提供開始されるでしょう。
思えば、検索画面にAI生成の回答が表示されるAI Overview(当初名称はSGE)が発表されたのがわずか1年少し前。そこから早くも、1年で検索を根底から変革するなんて、Googleは本気を出すと恐ろしい巨人です。
今回はAI Modeとは何か、SEOにどのような影響を及ぼすか、現状判明している範囲で解説します。
まずは基本!AI OverviewsとAI Modeって、結局なにが違うの?
 「AI Overviews?AI Mode?なんだか似ていてよく分からない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
「AI Overviews?AI Mode?なんだか似ていてよく分からない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、この2つの機能がそれぞれ「何」で「どんな目的」を持っているのか解説していきます。
「AI Overviews」は“AIアシスタント”
AI Overviews(AIによる概要)とは、一言でいえば「検索結果のトップに表示される、AIが作成した要約」です。ユーザーが知りたいことに対して、AIが複数のウェブサイトから情報を集め、「まずはこれだけ読めばOK」という形で簡潔にまとめてくれる便利な機能です。
日本では2023年8月から「SGE」という名前で試験的に導入されていました。そして2024年8月から「AI Overviews」として本格的にスタートしたのが現在の形です。
ユーザーにとっては、わざわざ色々なサイトを見に行かなくても、すぐに答えの要点がわかるので非常に便利です。そして、サイト運営者にとって最も重要なポイントは、このAIの要約には、情報源となったウェブページへのリンクが必ず表示されるという点です。ここに、大きなビジネスチャンスが隠されています。
「AI Mode」は“対話できる専門家”
AI Modeは、AI Overviewsよりもさらに一歩進んだ、対話形式のAI検索機能です。簡単な質問だけでなく、複雑な相談や比較検討、アイデア出しなど、まるで専門家と壁打ちするようにAIと会話しながら答えを探求できます。
AI Modeには、これまでの検索の常識を覆すような驚きの機能が搭載されています。
- テキスト以外の質問もOK(マルチモーダル入力): 例えば、スマートフォンのカメラで写した商品の写真を見せて「これと同じような商品で、もっと安いものを探して」と質問したり、製品パンフレットのPDFをアップロードして「この製品の長所と短所をまとめて」と頼んだりできます。
- 複雑な計画もおまかせ(高度な推論能力): 「来週末の家族旅行、小学生の子供が楽しめるプランを3つ提案して」といった、複数の条件が絡み合うような難しいお願いも、AI Modeなら一度で回答してくれます。
- より徹底的なリサーチ(Deep Search): 有料版の機能にはなりますが、「Deep Search」を使えば、特定のテーマについて数百ものサイトを横断的に調査し、数分で詳細なレポートを作成することも可能です。
現時点では、AI Modeは主にアメリカ、インドなどで先行して提供されており、日本ではまだ未提供です。
なぜ違いが重要?これからのサイト戦略の分かれ道
AI OverviewsとAI Modeの違いを、シンプルに例えるならこうです。
- AI Overviews は、あなたのために要点をまとめてくれる「優秀な秘書」
- AI Mode は、あなたと一緒に深く考える「頼れるリサーチパートナー」
AI Overviewsがユーザーの「効率」を重視するのに対し、AI Modeは「探求」をサポートします。この違いを理解することが、なぜそれほど重要なのでしょうか?
それは、それぞれのAIに評価され、選ばれるためのコンテンツ戦略が全く異なる可能性が高いからです。
これからのウェブサイトは、大きく分けて2種類のコンテンツを意識して作る必要があります。
- 「AI Overviews引用狙い」のコンテンツ:
AIがパッと見て理解し、要約に使いやすいように、結論から先に書き、Q&A形式を取り入れるなど、簡潔で分かりやすく構成されたコンテンツです。これは「〇〇とは?」のような、情報を手早く知りたいユーザーのニーズに応えます。 - 「AI Mode活用狙い」のコンテンツ:
AIが複雑な質問に答えるための「引き出し」として使えるように、独自のデータや詳細な事例、お客様の声など、他にはないユニークで深い情報を盛り込んだコンテンツです。これは、商品の比較検討や具体的な計画を立てたいユーザーのニーズに応えます。
つまり、Googleはユーザーの目的に合わせて、検索体験を2つの道に分けているのです。サイト側も、この両方の道に対応できるような二段構えの戦略が必要不可欠になるでしょう。
リスクをチャンスに変える
「結局のところ、うちのビジネスにどんな影響があるの?」AI検索がもたらす具体的なリスクと、それを乗り越えた先にある大きなチャンスについて、分かりやすく解説します。
最大のリスク:「ゼロクリック検索」でサイトへのアクセスが激減?
「ゼロクリック検索」は、ユーザーが検索結果ページに表示された答え(例えば、天気予報や簡単な定義など)だけで満足してしまい、どのウェブサイトもクリックせずに検索を終えてしまう現象のことです。
AI Overviewsは、このゼロクリック検索をさらに加速させる可能性があります。なぜなら、AIが生成する分かりやすい要約によって、ユーザーがGoogleのページから移動する必要がなくなってしまうからです。
特に、「〇〇 やり方」「〇〇とは」といった情報を調べるための検索では、AIが答えを要約しやすいため、サイトへのアクセスが減少しやすいと考えられています。
これまでSEO対策で上位表示させてきたページへのアクセスが、ある日突然減ってしまう…そんな未来も、決して絵空事ではないのです。
新たなチャンス:GoogleのAIに選ばれることの絶大な価値
しかし、悲観する必要は全くありません。むしろ、ここに大きなチャンスが眠っています。前述の通り、AI Overviewsは生成した要約の出典元として、必ずウェブサイトへのリンクを表示します。
AI Overviewsの要約内で自社のサイトが引用されることは、検索結果の一番上、いわば「新たな一等地」を獲得することを意味します。GoogleのAIが「信頼できる情報源」として自社サイトを選んでくれた、という事実は、ユーザーに対して絶大なブランドイメージと信頼性を与える効果があります。
これからのウェブサイトへのアクセスは、「量」より「質」が問われる時代になります。AIの要約を読んだ上で、「もっと詳しく知りたい」とクリックしてくれるユーザーは非常に意欲が高く、問い合わせや購入につながる可能性が高い「質の高い見込み客」と言えるでしょう。
さらに、この変化は専門分野に特化した中小企業にとって大きな追い風です。AIは、会社の規模や知名度だけでなく、「その質問に対して、最も的確で分かりやすい答えを提供しているか」を重視します。
これにより、深い専門知識を持つニッチな企業が、大手の競合サイトを飛び越えてAIに引用される「下剋上」が起こりやすくなると考えられます。
日本市場ならではの状況と対策のポイント
日本市場には、Yahoo! JAPANの人気が根強い、ビジュアル情報を好む傾向があるなど独自の特性があります。AI検索への対応も、こうした日本の状況を踏まえることが大切です。
AI技術は導入されたものの、AIが生成した回答に対するユーザーの信頼度は、まだ発展途上かもしれません。これは、競合他社に先駆けてAIO戦略を確立するための、貴重な時間的猶予があることを意味します。
特に、店舗やクリニックといった地域に根差したビジネスにとって、AI Overviewsは地域の情報(MEO対策など)と深く連携します。Googleマップの情報やローカル検索向けの情報が、これまで以上に重要になってくるでしょう。
SEOの次に来る新常識、AIO(AI最適化)をはじめよう
ここからは、本記事の核心である新のSEOとどう違うのか、そしてなぜ今、この考え方が重要なのかを理解することで、具体的な次の一手が見えてきます。
AIO(AI最適化)とはAIに理解され、引用されるための新技術
AIO(AI Optimization:AI最適化)とは、自社のウェブサイトの情報を、AI OverviewsのようなAIシステムが「理解」しやすく、「信頼」でき、そして「引用」したくなるように、コンテンツを作成・整理する一連の取り組みのことです。
その目的は、従来のSEOとは少し異なります。
- 従来のSEOの目的: 検索結果で上位に表示されること(1位の青いリンクを目指す)
- AIOの目的: AIが生成した回答の中で引用されること
これは、まるでAIアシスタントに分かりやすく説明してあげるようなアプローチです。キーワードをたくさん入れることよりも、ユーザーの質問にストレートに答える明快さや、情報の信頼性を証明することが何倍も重要になります。
AIOはSEOの進化形。土台があってこそ花開く
ここで非常に重要なのは、「AIOはSEOに取って代わるものではない」ということです。AIOは、これまでのSEOの努力の上に成り立つ、いわばSEOの進化形です。
サイトの表示速度、スマホ対応、そして質の高いコンテンツといった、優れたSEOの基本は、AIOを成功させるための大前提となります。しっかりとしたSEOの土台がなければ、AIOの効果は期待できません。
| 項目 | 従来のSEO | AI最適化(AIO) |
| 主目的 | 検索結果での上位表示 | AIの回答内での引用 |
| 意識する相手 | 検索エンジンのクローラー | 生成AIモデル(とその先のユーザー) |
| コンテンツの焦点 | キーワード、トピックの網羅性 | 質問への直接的な答え、独自の経験、データ |
| コンテンツの構造 | 長文記事、見出しの工夫 | Q&A形式、結論ファースト、論理的な構成 |
| 重要な指標 | アクセス数、クリック率、順位 | 引用された回数、引用経由のアクセスの質 |
| 基本思想 | どうすれば上位表示できるか? | この質問への最高の答えは何か? |
この比較表は、考え方のシフトを具体的に理解するのに役立ちます。「何をどう変えればいいのか?」という疑問への答えが、ここに詰まっています。
AIが生成する回答には、間違った情報を言ってしまう「ハルシネーション」という弱点があります。Googleがこのリスクを避けるためには、当然ながら信頼できる情報源を優先する必要があります。
その信頼性を判断するための最も重要な指標こそが、Googleが長年提唱してきた「E-E-A-T」です。
E-E-A-Tとは、以下の頭文字を取ったもので、コンテンツの品質を評価するための基準です。
- Experience(経験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trustworthiness(信頼性)
これまでもSEOで重要とされてきましたが、AI時代において、その価値は決定的なものになりました。
つまり、AIO戦略の根幹は、E-E-A-Tを徹底的に高め、自社がその分野の専門家であることをウェブサイト上で明確に示すことに他なりません。AIが自信を持って「このサイトの情報なら間違いない」と判断できるような、信頼性の高い情報発信こそが、最高のAIO対策となるのです。
「E-E-A-T」の視点でコンテンツを総点検
まず最初にやるべきことは、自社サイトのコンテンツがAIに信頼されるだけの品質を持っているかを確認することです。特に、AIには真似できない「Experience(経験)」、つまり自身の体験談やお客様の事例が、これからの時代、最も強力な武器になります。
具体的なアクションプラン:
- 「誰が」書いたか明確にする: 記事の著者情報を充実させましょう。「この記事は、この道15年のベテラン担当者が書いています」というように、著者の経歴や資格、実績をプロフィールに明記するだけで信頼性は格段にアップします。会社の代表や現場の専門スタッフが顔を出して語るのが理想的です。
- 「経験」をコンテンツに注入する: 実際に商品を使った感想、サービス導入後の顧客の変化、プロジェクトで苦労した話など一次情報を加えることで、コンテンツに命が吹き込まれます。
- 信頼できる情報で裏付けをする: 主張を補強するために、省庁の統計データや業界団体のレポート、学術論文など権威ある外部サイトへのリンクを適切に貼りましょう。
AIが引用したくなるコンテンツに書き換える
AIは、人間と同じように、整理整頓された分かりやすい文章を好みます。コンテンツの「構造」を少し見直すだけで、AIに選ばれる可能性は大きく変わります。
具体的なアクションプラン:
- 「結論ファースト」を徹底する: ユーザーが一番知りたいであろう「答え」を、記事の冒頭でズバリと書きましょう。例えば、「〇〇の選び方」という記事なら、「〇〇を選ぶ最も重要なポイントは、AとBとCの3つです」と最初に言い切ってしまうのです。
- 見出しを「質問形式」にする: ユーザーが実際にGoogleで検索しそうな「〇〇するにはどうすればいい?」といった疑問形の言葉をH2やH3の見出しに使ってみましょう。
- FAQ(よくある質問)を充実させる: サイト内にFAQページを設けたり、記事の最後にQ&Aコーナーを追加したりするのは非常に効果的です。
- シンプルで断定的な言葉を選ぶ: 難しい専門用語は避け、一文を短く、シンプルに。「〇〇の原因は△△です」のように、ハッキリとした表現を心がけましょう。
構造化データを設置する
構造化データと聞くと難しく感じるかもしれませんが、例えるなら「ウェブサイトの情報に、AI専用の名札をつけてあげる」ようなものです。
例えば、サイトに「株式会社〇〇 東京都千代田区1-1-1」と書くだけでなく、構造化データを使って「これは会社名です」「これは住所です」というAI向けの情報を裏側に追加します。
これにより、GoogleのAIはあなたのサイトの情報を100%正確に理解できるようになるのです。これは、AIとコミュニケーションを取るための最も確実な方法の一つです。
具体的なアクションプラン(まず実装したいTOP3):
- FAQPage(よくある質問): FAQページやQ&Aセクションに実装します。「ここにはユーザーの質問と、それに対する明確な答えがセットで書かれていますよ」とAIに教える効果があります。
- Organization / LocalBusiness(組織・地域ビジネス): 会社のトップページや概要ページに実装します。正式な会社名、住所、電話番号、ロゴなどをAIに正確に伝え、サイト全体の信頼性を高めます。
- Article(記事): ブログ記事やコラムに実装します。著者情報や公開日などをAIに伝えることで、E-E-A-Tの評価を高める手助けになります。
「専門的で難しそう…」と感じるかもしれませんが、WordPressなどのサイト作成ツールには、これを簡単に追加できるプラグイン(拡張機能)がたくさんあります。
まとめ
AI検索の登場は、ウェブサイト運営のルールを大きく変えようとしています。しかし、それは決して恐れるべきものではありません。むしろ、本質的な価値を提供している企業にとって、これまでにない大きなチャンスです。
これからは「キーワードで何位か?」だけでなく、「ユーザーのどんな質問に、最高の答えを返せるか?」を考えましょう。目指すは、あなたの専門分野で最も頼りになる情報源です。
さらに、E-E-A-Tを重視し、構造化された質の高いコンテンツを作ることは、今後登場するであろう、さらに進化したAIエージェントの時代にも通用する、普遍的で強力なウェブ戦略です。
これからの時代に成功するのは、小手先のテクニックではなく、ユーザー(そしてAI)に対して誠実に向き合い、真の専門知識と経験という価値を提供する企業です。
もし、本記事の内容を自社サイトに具体的にどう適用すれば良いか分からない、あるいは専門的な知見に基づいた個別のコンサルティングが必要だと感じられた場合は、どうぞ弊社スリードットにお気軽にご相談ください。経験豊富なコンサルタントが、お客様のサイト規模や特性に合わせた最適な戦略をご提案し、目標達成をサポートいたします。
弊社スリードットは、SEOを含めた総合格闘技としてWebマーケティングの支援をさせていただいております。最新のWebマーケティング情報収集、SEOの外注化、または内製化における伴走型サポートに興味ある方は弊社にお気軽にご相談ください。