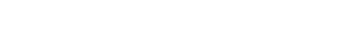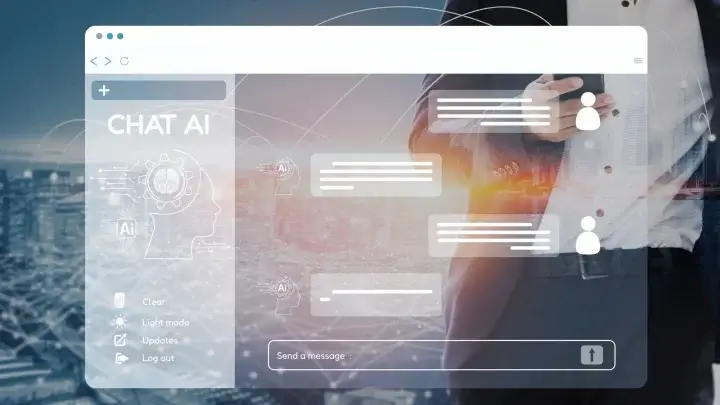
AI OverviewなどAI検索の登場により、ユーザーが情報を得るプロセスは根底から変わりつつあります。従来の検索エンジン最適化(SEO)だけでは、もはや十分とは言えない時代が到来しました。
ユーザーはもはや、断片的なキーワードで検索するだけではありません。「自社の課題を解決してくれるサービスは何か」といった、より自然で対話的な形でAIに問いかけるようになっています。
これからの戦場は、AIが生成する「回答」そのものの中に自社の製品やサービスを引用させ、言及させるLLMO(大規模言語モデル最適化)が新たな競争軸となります。
この記事は、多くの企業様のWebマーケティングを支援しているスリードット株式会社のコンサルタントが、AI時代の新たなマーケティング手法LLMOとGoogleがコンテンツの品質を評価する上で重視するE-E-A-Tという2つの概念を深く掘り下げ、両者がいかに密接に結びついているかを解き明かします。
目次
なぜE-E-A-TがLLMOの絶対的な前提条件なのか
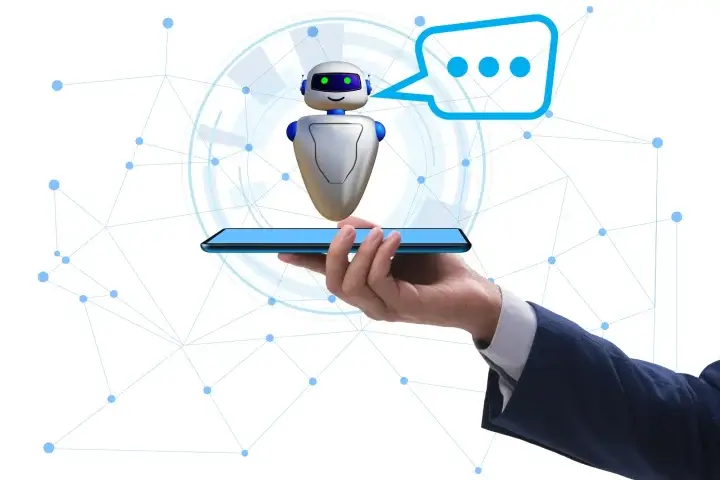
新たな戦略を構築する上で、まずはその核となる概念の共通認識を持つことが不可欠です。ここでは、E-E-A-TとLLMOという2つのキーワードを、単なる専門用語としてではなく、ビジネス戦略に直結する実践的なフレームワークとして解説します。
E-E-A-TとはGoogleが定義する信頼のフレームワーク
E-E-A-Tとは、Googleがウェブサイトやコンテンツの品質を評価するために用いる基準であり、以下つの英単語の頭文字をとったものです。これはGoogleの検索品質評価ガイドラインに明記されており、検索アルゴリズムが目指す方向性を示す重要な概念です。
| E-E-A-T | 問われていること | 具体的な評価内容 |
|---|---|---|
| Experience(経験) | 「実際にそれをやったことがあるか?」 | 製品を実際に使用したレビュー、特定のサービスを導入したプロセス、ある場所を訪れた実体験など一次情報に基づくリアルな知見が問われます。 |
| Expertise(専門性) | 「その分野に精通しているか?」 | 特定のトピックに関する深い知識やスキル、網羅的な情報提供能力が評価されます。 |
| Authoritativeness(権威性) | 「その分野の第一人者として認められているか?」 | 業界内での評判や、他の専門家からの引用、公的な受賞歴など第三者からの評価が重要になります。 |
| Trustworthiness(信頼性) | 「その情報やサイトは信頼できるか?」 | 情報の正確性、サイトの安全性(SSL化)、運営者情報の透明性などユーザーが安心して利用できる基盤そのものが評価の中心となります。 |
重要なのは、E-E-A-Tが検索順位を直接操作する個別の「ランキング要因」ではないという点です。むしろ、Googleの自動評価システムが「高品質でユーザーにとって有益なコンテンツ」を判断するために用いる「思考の枠組み」と理解するべきです。
この枠組みに沿ってコンテンツを構築することが、結果的に検索エンジンからの高い評価につながります。
LLMOとはキーワードではなく対話への最適化
LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)とは、ChatGPTやGoogleのAI Overview(旧SGE)といった生成AIが回答を生成する際に自社のウェブコンテンツが情報源として優先的に引用・参照されるように最適化を行う一連の施策を指します。
従来のSEOが「キーワード検索」というユーザー行動を起点としていたのに対し、LLMOは「自然言語での質問・対話」を起点とします。例えば、ユーザーが「おすすめの会計ソフトは?」とAIに尋ねた際に、自社製品がその回答内で推奨され、公式サイトへのリンクが引用されるのがLLMOが目指すゴールです。
LLMOは、AIという新たな「情報仲介者」に対して、自社がいかに信頼に足る情報源であるかを証明するためのブランド戦略に近いアプローチが求められるのです。
AIはE-E-A-Tが高いコンテンツから実体験や独自知識を借用する
LLMOで成功を収めるためには、E-E-A-Tという強固な土台が不可欠です。なぜなら、生成AIモデルは、その設計思想の根幹に「信頼性」と「正確性」の追求を組み込んでいるからです。
AIは自ら経験したり、独自の専門知識を持ったりするわけではありません。その知識はすべて、ウェブ上に存在する膨大な学習データに基づいています。
そのため、AIが回答を生成する際には、学習データの中から「最も信頼できる情報源」を見つけ出し、それを基に回答を組み立てる必要があります。
この「信頼できる情報源」かどうかを判断するための重要なシグナルこそが、E-E-A-Tなのです。AIは、明確な経験に基づき、専門性が高く、業界での権威が認められ、全体として信頼できるサイトからの情報を優先的に参照します。
つまり、E-E-A-Tを高める取り組みは、Googleの検索エンジンだけでなく、AIモデルに対しても自社の信頼性をアピールする上で効果的な手段となるのです。
AI特有のハルシネーション回避にE-E-A-Tは欠かせない
生成AIが抱える最大のリスクの一つに、「ハルシネーション(Hallucination)」、つまり事実に基づかないもっともらしい嘘を生成してしまう現象があります。AIサービスの提供者にとって、ユーザーに誤情報を提供することは、そのサービスの信頼性を根底から揺るがす致命的な問題です。
したがって、AIモデルは「間違ったことを言いたくない」という強い動機を持っており、回答を生成する際には、その根拠となる情報源を極めて慎重に選びます。
AIにとって、ハルシネーションのリスクを冒して不確かな情報を組み合わせるよりも、E-E-A-Tの高い単一の信頼できる情報源を引用する方がはるかに安全な選択となります。
自社のコンテンツをAIにとっての「安全な避難場所」として確立することで、引用・参照される確率を劇的に高めることができるのです。
この文脈で重要になるのが、単にキーワードを配置するのではなく、Googleが提唱する「誰が(Who)、どのように(How)、なぜ(Why)」という問いに明確に答えられるコンテンツを用意することです。つまり、その主張を裏付ける客観的な証拠をウェブ上に構築していく作業が中心となります。
AI生成コンテンツの洪水だからこそ発信者の信頼性が問われる
AIライティングツールの普及により、誰でも、安価に、大量のコンテンツを生成できる時代になりました。ウェブ上の情報は爆発的に増加し、まさに情報の洪水ともいえる状況が生まれています。
コンテンツの量だけでは、もはや差別化は不可能です。
このような環境下でAIが次に重視するのは「その情報は“誰が”発信しているのか?」という問いです。
無数のAI生成コンテンツと、人間による経験と専門知に裏打ちされたコンテンツを区別する上で発信源の信頼性は決定的な意味を持ちます。E-E-A-Tは、この「誰が」という問いに答えるための最も強力なフレームワークです。
明確な著者情報、専門的な経歴、第三者からの評価といったE-E-A-Tの各要素がコンテンツの真正性を証明し、その他大勢のノイズから際立たせるための唯一無二の指標となるのです。
教師データになることによる未来への投資
少し長期的な視点に立つと、E-E-A-Tの重要性はさらに増します。GoogleをはじめとするAI開発企業は、次世代のAIモデルを開発する際、ウェブ上のどの情報を「教師データ」として学習させるでしょうか。
言うまでもなく、E-E-A-Tが高いと評価された、高品質で信頼性の高い情報群を選ぶはずです。
自社のコンテンツが、この「信頼できる教師データセット」の一部となることは、自社の専門知識やブランドがAIの知識基盤に組み込まれることを意味します。これは、単に目先のトラフィックを獲得する以上の、計り知れない戦略的価値を持ちます。
今、E-E-A-Tに投資することは、AI時代における自社のブランドの永続的な権威性を構築するための投資に他ならないのです。
LLMOにおけるE-E-A-T実装:Experience (経験)

2022年12月にGoogleがE-A-Tに「Experience(経験)」を追加したことは、AI時代の到来を象徴する出来事でした。これは、AIが生成した一般的な情報と、人間による一次的な実体験に基づく情報を明確に区別し、後者を高く評価するというGoogleの意思表示です。
LLMOにおいて「経験」は、最大の差別化要因となります。実践的な戦略としては以下が重要です。
独自データの公開
以下のようなデータを分析し、独自のインサイトとして公開します。
- 自社で実施した市場調査
- 顧客アンケートの結果
- 自社サービスから得られた匿名化された利用動向データ
これは、他社が容易に模倣できない、極めて価値の高い一次情報です。
詳細なケーススタディの作成
単なる成功事例の紹介に留まらず、以下を詳細に記述します。
- 「顧客が抱えていた具体的な課題」
- 「それを解決するためにどのようなプロセスを辿ったか」
- 「途中で直面した困難とそれをどう乗り越えたか」
- 「最終的に得られた定量的・定性的な成果」
物語性のある具体的なプロセスは、AIには生成不可能です。
現場の知見(”In-the-Trenches” Insights)の共有
成功談だけでなく、実際のプロジェクトで学んだ教訓や時には失敗から得た知見も率直に共有します。こうした情報は、読者からの強い共感と信頼を生み出し、コンテンツの真正性を際立たせます。
実践的な製品・サービスレビュー
もし製品やサービスを評価するコンテンツを作成する場合、スペックシートを要約するのではなく、実際にそれらを長期間使用し、具体的な使用感、メリット、そして改善点などを写真や動画を交えて詳細にレポートします。
LLMOにおけるE-E-A-T実装:Expertise (専門性)
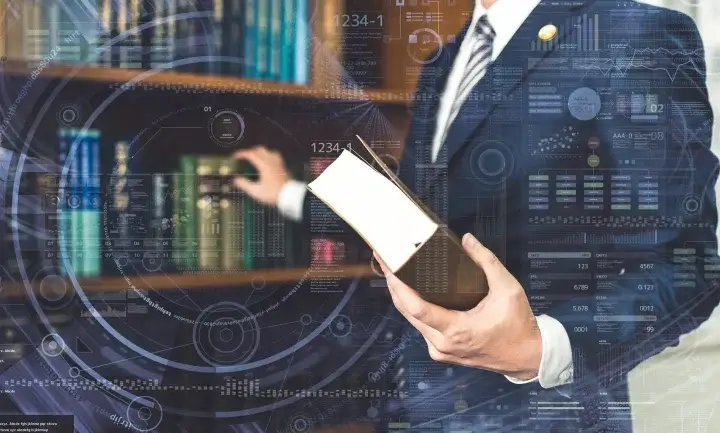
LLMOにおける専門性とは、特定のトピックについて、広く、深く、そして正確に語れる能力を指します。AIは断片的な情報をつなぎ合わせるよりも、一つのテーマに関連するトピックを体系的かつ網羅的に解説しているコンテンツを信頼性の高い情報源として評価する傾向があります。
実践的な戦略として以下が挙げられます。
トピッククラスターモデルの展開
一つの中心的なテーマ(例:「BtoBマーケティングオートメーション」)について、包括的な解説を行う「ピラーページ」を作成します。
そして、そのテーマに関連するより具体的なサブトピック(例:「リードナーチャリング手法」「スコアリングモデルの作り方」)に関する詳細な「クラスターページ」を複数作成し、それらをピラーページに内部リンクで結びつけます。
この構造は、サイト全体でそのテーマを網羅していることをAIに明確に伝えます。
自明の理を超えた洞察の提供
誰でも知っているような一般的な情報を羅列するのではなく、独自の分析や、異なる事象を結びつけるような深い洞察を加えます。読者が記事を読み終えた後に「なるほど、そういう見方があったのか」と感じるような付加価値の高い情報を提供することが重要です。
権威ある情報源の引用
自社の主張を裏付けるために、官公庁、大学、研究機関などが発表している統計データや研究結果を引用します。その際は、必ず出典元を明記し、リンクを設定することで情報の正確性と誠実な姿勢を示します。
LLMOにおけるE-E-A-T実装:Authoritativeness (権威性)

権威性とは、コンテンツそのものの品質だけでなく、「誰が、どの組織が」その情報を発信しているかという、外部からの評価によって形成されます。その分野の第一人者として、業界内外から広く認知されている状態を目指します。
実践的な戦略は以下です。
著者・運営者情報の徹底的な拡充
記事の著者ごとに、顔写真、経歴、保有資格、過去の執筆実績、SNSアカウントなどを網羅した詳細なプロフィールページを作成します。
同様に、サイト運営企業についても、事業内容、沿革、経営陣の紹介、企業理念などを記載した「会社概要」ページを充実させます。これは、情報の透明性を高め、信頼の基盤となります。
戦略的なPR・メディア露出
業界で評価の高い専門メディアやニュースサイトからの取材、経営者や専門家による寄稿、業界カンファレンスでの登壇などを積極的に行います。こうした第三者からの評価や言及(サイテーション)は、権威性を客観的に証明する強力なシグナルです。
質の高い被リンクとサイテーションの獲得
関連性の高い権威あるウェブサイトから自然な形でリンクを獲得したり、リンクなしで言及されたりすることを目指します。これは、コンテンツの価値が他者から認められている証拠となります。
LLMOにおけるE-E-A-T実装:Trustworthiness (信頼性)

信頼性はE-E-A-Tの中心的な要素であり、他のすべての取り組みを支える土台です。ユーザーが安心してサイトを閲覧し、そこに書かれている情報を信じ、問い合わせなどの行動を起こせるか、というサイト全体の健全性が問われます。
実践的な戦略 として以下が挙げられます。
技術的な信頼シグナル
サイト全体の常時SSL化(HTTPS対応)は、もはや必須のセキュリティ対策です。ユーザーのデータを保護する基本的な姿勢を示します。
運営の透明性
企業の正式名称、物理的な住所、連絡可能な電話番号、そして問い合わせフォームへの導線をサイトのフッターなど分かりやすい場所に常に明記します。プライバシーポリシーや利用規約を制定し、公開することも不可欠です。
情報の正確性と訂正ポリシー
コンテンツ内の情報が事実に基づいていることを保証し、万が一誤りがあった場合には迅速に訂正・追記を行うプロセスを確立し、その旨をサイト上で明記します。
明確な情報源の提示
統計データや他者の見解を引用・参照する際は、必ずその出典元を明記し、誠実な情報提供の姿勢を貫きます。
E-E-A-TをAIに伝えるために実装すべき技術

E-E-A-Tという戦略的な概念を構築したら、次はその価値をAIモデルに正確かつ効率的に伝えるための技術的な実装が必要です。ここでは、LLMOに不可欠な2つの技術的要素を解説します。
構造化データ(Schema.org)
構造化データ(スキーママークアップ)とは、ウェブページのコンテンツが「何であるか」を検索エンジンやAIに明確に伝えるための「語彙」のようなものです。例えば、ページ上の「田中太郎」という文字列が「人物(Person)」であり、この記事の「著者(author)」であることを機械が解読できる形式で伝えることができます。
Googleは、この実装方法としてJSON-LD形式を推奨しています。
Personスキーマ
著者の信頼性を確立するために使用します。name(氏名)、jobTitle(役職)、alumniOf(出身校)、worksFor(所属組織)といったプロパティに加え、特に重要なのがsameAsです。
sameAsを用いて著者のLinkedInプロフィール、X(旧Twitter)アカウント、所属団体の紹介ページなど、その人物を特定できる権威あるURLと関連付けます。そうすることで、ウェブ上に分散した情報を統合し、検証可能な「エンティティ(実体)」としてAIに認識させます。
Organizationスキーマ
コンテンツの発行元である組織の信頼性を確立します。以下を用いて企業の公式SNSアカウントや第三者評価サイトのページを関連付けます。
- name(組織名)
- legalName(法人名)
- logo(ロゴ画像のURL)
- address(住所)
- sameAs
Articleスキーマとauthor/publisherのネスト
これらすべてを統合するのがArticleスキーマです。記事のauthorプロパティにPersonスキーマを、publisherプロパティにOrganizationスキーマを「ネスト(入れ子に)」することで「この専門的な記事は、この信頼できる組織に所属する、この特定の専門家によって書かれました」という明確な関係性をAIが誤解の余地なく理解できるようになります。
llms.txt
llms.txtはLLMOのために提案されている新しいウェブ標準です。llms.txtはMarkdownというシンプルなテキスト形式で記述します。
llms.txtは、AIに対してウェブサイトの構造化されたコンテンツにアクセスし、解釈しやすくするためのガイド役を果たします。AIに対して「ようこそ、当サイトの重要な情報はこちらです」と案内する「コンシェルジュ」のような役割を担います。
llms.txtはまだ新しい概念ですが、これをウェブサイトのルートディレクトリに設置しておくことはAIクローラーに対して直接的かつ効率的に情報を伝えるための取り組みです。
まとめ
本稿で詳述してきたように、生成AIが検索体験の中心となる時代において、ウェブサイトの可視性は「信頼」の構築そのものです。そして、その信頼の通貨となるのがE-E-A-Tです。
LLMOとE-E-A-Tへの取り組みが目指すべき最終的なゴール、それは「AI指名ブランド」になることです。これは、ユーザーからの問いに対して、AIモデルが優先的にあなたの会社、製品、そして知見を「指名」して推薦してくれる状態を指します。
E-E-A-Tを単なるSEOのチェックリストとして捉えるのではなく、AI時代におけるブランドの永続的な権威性と競争優位性を築くための、最も重要な経営投資として位置づけましょう。その視点が、これからのデジタルマーケティングで勝ち残るための第一歩となるでしょう。
よくある質問
E-E-A-Tは、YMYL(Your Money or Your Life)と呼ばれる金融や健康などの特定の分野だけで重要なのでしょうか?
YMYL分野でE-E-A-Tが特に厳しく評価されるのは事実ですが、その重要性はあらゆる分野に及んでいます。Googleのドキュメントでは、トピックに関わらず、E-E-A-Tを示すことはコンテンツの信頼性を確立し、他との差別化に役立つとされています。
特に「経験(Experience)」は、製品レビューから旅行記まで、ほぼすべてのトピックで価値があると見なされています。AIが情報源の信頼性を重視するLLMOの文脈では分野を問わずE-E-A-Tは成功の基盤となります。
中小企業でリソースが限られている場合、E-E-A-Tの4つの要素の何から優先的に着手すべきですか?
すべての要素は相互に関連していますが、リソースが限られる場合は「信頼性(Trustworthiness)」と「経験(Experience)」から着手することをおすすめします。
まず、サイトのSSL化や運営者情報の明記といった「信頼性」の土台を固めることは、比較的低コストで実行可能な必須項目です。次に、大企業にはない独自の「経験」、例えば地域に密着した顧客とのエピソードやニッチな分野での長年の実践から得た知見などをコンテンツ化することで、AIにも模倣できない独自の価値を生み出すことができます。
Personスキーマを実装する際、著者個人のSNSアカウントなどをsameAsで紐づけることに抵抗があるのですが、必須でしょうか?
必須ではありませんが強く推奨されます。sameAsプロパティの目的は、ウェブ上に散らばる情報を結びつけ、その人物が実在し、一貫した専門性を持つ「エンティティ」であることをAIに証明することです。これにより、権威性と信頼性が大幅に向上します。
もし個人のSNSに抵抗がある場合は、企業の公式プロフィールや、LinkedIn、業界団体の会員ページ、登壇したイベントの紹介ページなど、専門性を示すことができる公的なURLを紐づけることから始めるのが良いでしょう。重要なのは、その人物が誰であるかを客観的に検証できるシグナルを提供することです。