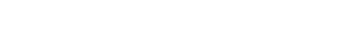ChatGPTをはじめとする生成AIの話題が日々メディアを賑わせる中、「自社のWebマーケティング戦略はこのままで大丈夫だろうか?」と漠然とした不安を感じている経営者やWeb担当者の方は少なくないでしょう。
LLMO(大規模言語モデル最適化)という新しい言葉も登場し、具体的に何をすべきか分からず、情報収集に追われているかもしれません。
本記事では、多くの企業様のWebマーケティングを支援しているスリードット株式会社のマーケティングコンサルタントが、LLMOの基本からSEOとの決定的な違い、そして明日から実践できる具体的な対策までわかりやすく解説します。この記事を読み終えれば、LLMOはSEOと対立するものではなく、これまで積み上げてきた努力を活かせる強力な「味方」であることがご理解いただけるはずです。
まずは結論:LLMOはSEOの敵ではなく進化形

LLMO(大規模言語モデル最適化)は、SEO(検索エンジン最適化)を過去のものにするのではなく、むしろその土台の上に成り立つ「進化形」です。
なぜなら、生成AIも信頼できる情報を得るために、検索エンジンで高く評価されているWebサイトを参考にすることが多いからです。
したがって、取り組むべきは「SEOか、LLMOか」という二者択一ではありません。「SEOを土台としながら、LLMOの視点を取り入れて戦略をアップデートする」ことこそが、これからの時代に求められる正しいアプローチなのです。
LLMO(大規模言語モデル最適化)とは?
LLMOとは、Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)の略称です。具体的には、ChatGPTやGoogleのAI Overviews(AIによる概要)といった生成AIがユーザーの質問に回答を生成する際に、自社の情報やコンテンツがAIに引用・参照されたり、好意的に言及されるように、Webサイトや関連情報を最適化する一連の施策を指します。
従来のSEOは「検索結果のリスト(青いリンク)で上位に表示され、クリックしてもらう」ことを目的としていました。一方、LLMOは「AIが生成する回答そのものに、信頼できる情報源として組み込まれる」ことを目指します。
SEOとLLMOの共通点
ここまでSEOとLLMOの違いを解説してきましたが、これまでのSEOの知識や築き上げてきた資産は、LLMO時代にも大きな強みとなります。
信頼性と専門性の重視は共通
どちらの最適化においても、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を意識した質の高いコンテンツが評価されるという点は共通しています。AIもまた、信頼できる情報源として検索エンジンで高く評価されているサイトを参照する傾向があるためです。
構造化データの活用は共通
コンテンツの意味をAIや検索エンジンに明確に伝えるための構造化データは、SEOのリッチリザルト表示だけでなく、LLMOにおいてもAIの正確な情報理解を助けるために極めて重要です。
ユーザーの課題解決という目的は共通
最終的にユーザーの疑問や課題を解決するための情報を提供するというゴールは、SEOもLLMOも同じです。そのアプローチが「検索結果」経由か「AIの回答」経由かの違いに過ぎません。
SEOとLLMOの違いとは?

LLMOがSEOの進化形であると述べましたが、両者には明確な違いも存在します。この違いを正しく理解することが、効果的な戦略を立てる上での第一歩です。
【重要】SEO vs LLMO 戦略比較表
両者の違いをより明確にするために、以下の比較表にまとめました。この表は、今後の戦略を考える上での重要な指針となります。
| 観点 | 従来のSEO | LLMO |
|---|---|---|
| 主な目的 | 検索結果で上位表示され、クリックを獲得し、サイトへ流入させる | AIの回答内で引用・言及・推薦され、ブランド認知と信頼性を向上させる |
| 対象プラットフォーム | Google, Bingなどの検索エンジン | ChatGPT、Gemini、Perplexity、GoogleのAI Overviewsなどの大規模言語モデル(LLM)が組み込まれているプラットフォーム |
| コンテンツの焦点 |
|
|
| 主要な戦術 |
|
|
| 成果指標 |
|
AI回答での引用・言及回数、指名検索数の増加、ダイレクト流入数の増加 |
| 時間軸 | 比較的短期(数週間〜数ヶ月)で順位変動が見られることもある | AIの学習サイクルに依存するため、中長期的な視点(数ヶ月〜半年以上)が必要 |
目的が「クリックされる」から「引用・推薦される」へ
最も大きな違いは「目的」です。SEOの主目的は、検索結果で上位に表示され、ユーザーにクリックしてもらい、自社サイトへトラフィックを誘導することでした。
一方、LLMOの主目的は、AIの回答の中で自社の情報が引用・参照されたり、サービスが推薦されたりすることです。その結果として、以下の効果を狙います。
- ユーザーがブランド名を認知
- 後から指名検索
- サイトに直接アクセス
直接的なクリックではなく、AIを介した「信頼の獲得」がゴールとなります。
アルゴリズムの評価からAIの文脈理解と信頼性評価へ
最適化の対象が変わることで、評価される基準も変化します。SEOは、Googleの検索アルゴリズムが評価する様々なランキング要因(キーワードの関連性、被リンク、ページの表示速度など)に対応することが中心でした。
これは「検索エンジンにいかに評価されるか」という視点でのアプローチです。
対してLLMOでは、AIが情報の「文脈」をどれだけ正しく理解できるか、そしてその情報源がどれだけ「信頼」できるかが評価の軸となります。AIは以下の要素などを複合的に見て、引用すべき情報源を判断していると考えられています。
- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の高さ
- 情報の明確さ
- 構造化されたデータ
- ブランドとしての評判
LLMOの戦術は、「AIにいかに正確な情報を提供し、信頼できる情報源だと認識させるか」という視点にシフトします。リンクの有無に関わらずブランド名が言及される「サイテーション」を増やすことなどが主要な戦術となります。
コンテンツの焦点がキーワード網羅から情報の明確性へ
SEOコンテンツでは、特定のキーワードに対してユーザーが知りたいであろう情報を網羅的に含めて検索意図を満たすことが重視されてきました。人間が読み進めやすいように、ストーリー性や構成の巧みさも評価の対象でした。
一方、LLMOでは、AIが情報を「部品」として抽出し、回答を再構成しやすい形であることが求められます。そのため、曖昧な表現を排し、事実に基づいた情報を簡潔かつ明確に記述することが重要になります。
特に、ユーザーがAIに投げかけるような「〇〇とは?」といった問いに対して、直接的な答えを提示するQ&A形式のコンテンツはAIに引用されやすい理想的な形と言えるでしょう。
成果指標が直接的な流入数から間接的なブランド認知へ
SEOの成果は、以下のような比較的測定しやすく直接的な指標(KPI)で評価されてきました。
- 検索順位
- クリック率(CTR)
- オーガニック検索からの流入数
- コンバージョン数
しかしLLMOでは、AIの回答内で引用されても、ユーザーがサイトをクリックせずに満足してしまう「ゼロクリック検索」が増えています。そのため、直接的な流入に繋がらないケースが多くなります。
そのため、成果指標は、以下のような直接測定が困難なものが中心となります。
- AIの回答における引用・言及回数
- 指名検索数の増加
- ダイレクト流入の増加
これらの指標は直接的な効果測定が難しく、LLMOの成果評価を複雑にする一因となっています。
短期的な順位変動から中長期的な信頼構築へ
SEOは、アルゴリズムのアップデートや施策の内容によっては、数週間から数ヶ月といった比較的短い期間で検索順位の変動が見られることがあります。
もちろん、SEOも中長期的な取り組みが基本です。しかし、短期的な成果を追うことも不可能ではありませんでした。
対してLLMOは、AIがWeb上の情報を学習し、その知識ベースを更新するサイクルに依存します。そのため、施策の効果が反映されるまでに時間がかかります。
最低でも数ヶ月から半年以上という、より長期的な視点で取り組む必要があります。LLMOは短期的な順位を競うゲームではなく、時間をかけてAIとユーザーからの「信頼」をじっくりと築き上げていく活動なのです。
今すぐLLMOに応用できる5つのSEO施策

これまで皆さんが実践してきたSEO施策の多くは、少し視点を変えるだけで強力なLLMO対策になります。特に以下の施策は親和性が高く、すぐにでも応用が可能です。
E-E-A-Tのさらなる徹底
E-E-A-TはSEOでも重要でしたが、LLMOではさらに決定的な要素となります。以下を明確にすることが、AIに「信頼できる情報源」と認識させるための大前提です。
- 誰が書いたのか(経験・専門性)
- そのサイトは信頼できるのか(権威性・信頼性)
著者情報や監修者のプロフィールを詳細に記載し、その分野の専門家であることを明確にしましょう。
他のサイトの情報をまとめただけのコンテンツは、AIにとっても価値が低いと判断されがちです。そのサイトでしか得られない以下のような一次情報・独自情報を提供することが、引用される確率を格段に高めます。
- 自社で行った調査データ
- 独自の分析
- 具体的な導入事例
- 専門家としての見解
上記のような情報を盛り込むことが、AIに「信頼できる情報源」と認識させる上で非常に効果的です。
構造化データの戦略的実装
構造化データとは、Webページの内容(例えば、それが「よくある質問」なのか、「企業情報」なのか、「記事」なのか)を検索エンジンやAIが理解できる共通の言語(スキーマ)でタグ付けすることです。これはAIにとって、コンテンツを理解するための「カンニングペーパー」のような役割を果たします。
特に「FAQPage」「Article」「Organization」といったスキーマは、AIがQ&Aや記事内容、企業情報を正確に理解する手助けとなります。AIに引用されやすい形に情報を整理する意識で実装しましょう。
サイトパフォーマンスの最適化
Core Web Vitalsに代表される表示速度の改善は、ユーザー体験だけでなく、AIがサイト情報を収集する際の効率にも影響します。ページの表示速度が遅いと、AIがサイトの情報を収集するクローラーが内容を十分に読み込む前に離脱してしまう可能性があります。
AIにとっても快適なサイト環境を維持することは基本的なLLMO対策の一つです。GoogleのPageSpeed Insightsなどを活用して、表示速度を改善しましょう。
Q&Aコンテンツの拡充
ユーザーがAIに投げかけるような自然な疑問文を見出しにしたFAQコンテンツは非常に有効になります。例えば、「〇〇とは?」や「〇〇の選び方は?」と言ったスタイルの見出しです。
AIが回答を生成する際に直接引用しやすいからです。
質の高い被リンクとサイテーションの獲得
権威あるサイトからの被リンクや、文脈に沿ったブランド名・サービス名の言及(サイテーション)は第三者からの評価の証です。リンクがなくても、特定のトピックにおいて自社のブランド名やサービス名が頻繁に言及されていると、AIはその関連性を学習します。
これは検索エンジンだけでなく、AIがサイトの信頼性を判断する上でも強力なシグナルとなります。以下が効果的な手法です。
- 質の高い情報発信を起点としたデジタルPR
- 業界メディアへの寄稿
- SNSや専門家コミュニティで自然に名前が挙がるような、価値ある情報やサービスの提供
LLMOで最終的に重要になるのは、Webサイト単体の評価だけでなく、インターネット全体における「ブランドとしての信頼性」です。
エンティティの一貫性
エンティティとは、AIが認識する「特定の概念や存在(企業、製品、人物など)」を指します。AIに自社を正しく一つの存在として認識させる上で重要です。
自社サイト、SNS、Wikipedia、さまざまなWebメディアなど、インターネット上のさまざまなチャネルで、企業名や住所、サービス内容などの情報が常に統一されているようにしましょう。
SEO資産を最大化するLLMOへの戦略的移行5ステップ

すでにあるSEO資産を活かし、スムーズにLLMOへ対応していくためには、段階的なアプローチが有効です。
1:既存SEO施策の棚卸しと強化
まずは、E-E-A-TやテクニカルSEOといった基本を徹底することから始めましょう。土台がしっかりしているサイトほど、LLMO施策の効果も出やすくなります。
2:既存コンテンツのLLMO視点でのリライト
すでに上位表示されている記事やアクセス数の多いページから優先的に、LLMOを意識したリライトを行います。「結論ファースト」の構成にしたり、Q&A形式のセクションを追加したりするだけでも効果が期待できます。
3:問いを起点とした新規コンテンツ企画
キーワード起点だけでなく、「ユーザーがAIにどのような質問をするか」を起点にコンテンツを企画します。顧客からよく受ける質問やSNSでの疑問などを参考に、AIが回答したくなるようなコンテンツを作成しましょう。
LLMOの核となるのは、AIが情報を正確に、そして容易に理解できるコンテンツを作成することです。
AIはユーザーの質問に対する「直接的な答え」を探しています。記事の冒頭や各見出しの直後で結論を先に述べ、一文を短く、平易な言葉で記述することを心がけましょう。
AIが回答として文章をそのまま抽出しやすい形が理想です。
4:テクニカル最適化(AIに”正しく”サイト構造を伝える)
どれほど質の高いコンテンツがあっても、その構造がAIに正しく伝わらなければ効果が十分に発揮されません。ここでは、テクニカルな最適化という側面から、AIの理解を助けるための施策を紹介します。
- 構造化データの実装
- サイトパフォーマンスの最適化
- llms.txtの設置
llms.txtは現時点ではまだ標準化されていませんが、今後を見据えた新しい取り組みです。たとえば、「robots.txt」は検索エンジンのクローラーにサイトのクロールルールを伝えるのに使われますが、「llms.txt」はAIに対してサイトの概要や利用方針などを伝えるファイルとして検討されています。
自社サイトが何について書かれたサイトなのかを簡潔に記述しておくことで、AIがサイトの全体像を把握する手助けになると期待されています。
5:SEOとLLMOの両輪での効果測定
従来の検索順位や流入数に加え、指名検索数の増加やAIチャットでの自社言及を手動で確認するなど、LLMOの指標も合わせて定点観測し、PDCAサイクルを回していくことが重要です。
まとめ
本記事では、AI時代の新しいWebマーケティング戦略であるLLMOについて、その本質から具体的な実践方法までを解説しました。
改めて、重要なポイントを振り返ります。
- LLMOはSEOの進化形であり、従来のSEOで積み重ねてきた資産は今後も十分に活かすことができ、むしろLLMOの大きな土台となる
- 「コンテンツの明確性」「技術的な健全性」「ブランドの権威性」という3つの柱をバランス良く強化することが不可欠
AIの進化は大きなチャンスでもあります。まだ多くの企業が手探りの今、いち早く本質を理解し、正しい努力を始めることで競合に対して大きな優位性を築くことが可能です。
まずは自社サイトの主要ページを一つ選び、本記事で紹介した「結論ファースト」や「Q&A形式」といったコンテンツ作成のポイントを参考に、内容を見直してみるところから始めてみてください。
もし、自社だけでの推進に不安を感じたり、専門的な知見に基づいた戦略立案を求めていたりする場合は、ぜひ一度、私たちにご相談ください。貴社のビジネスに最適なLLMO戦略を共に描き、AI時代の成功をサポートします。
よくある質問
LLMOと従来のSEOの最も大きな違いは何ですか?
最も大きな違いは最適化の「対象」です。従来のSEOがGoogleなどの「検索エンジン」で上位表示されることを目指すのに対し、LLMOはChatGPTなどの「AI」が生成する回答の中で引用・言及されることを目指すという点にあります 。
予算やリソースが限られていますが、LLMO対策としてまず何から始めるべきですか?
まずは費用をかけずにできることから始めましょう。既存の重要記事を「結論ファースト」で書き直したり、想定される質問と回答(Q&A)の形式でコンテンツを追加したりするだけでも、AIに引用されやすくなります 。また、Googleの無料ツールを使って、サイトの構造化データが正しく実装されているかを確認することも、簡単で効果的な第一歩です 。