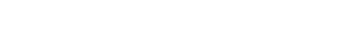「アクセス数が伸びてます!PVも順調です!」
毎月届くレポートに書かれた数字を見てもアクセス数は確かに増加、だいたいの項目が順調に伸びている…。でも本当にそれで心から納得していますか?
- 現場の体感はどうですか?
- 売上は比例して伸びていますか?
- お客様は本当に増えていますか?
「まあ、少しは効果が出ているはず…」「時間がかかるものだから…」「担当者も一生懸命やってくれているし…」どこかで自分に言い聞かせていませんか?
思い出してください。なぜ、そもそもWEB集客に投資しようと決めて、毎月コンサル料や作業料を支払おうと決裁したのでしょうか?
- 「売上を伸ばしたい」
- 「集客数を増やしたい」
そう、これが本当の目的だったはずです。
アクセス数やCV(成約数)という指標は、あくまでも「手段」であって「目的」ではありません。それは事業の本質とは別の話です。
この記事では、WEB集客の「効果測定の本質」についてお伝えします。アクセス解析から売上につなげるための具体的な方法、現場の数字とWEBの数値を正しく結びつける手法、そして効果的な改善の進め方まで、実践的な内容をご紹介します。
いつまでも「なんとなく」を続けるのか、それとも本質的な改善に踏み出すのか。その判断の材料を、この記事から得ていただければ幸いです。
目次
アクセス数が売上に結びつかない理由は?

「月次レポートではアクセス数が右肩上がりなのに、なぜか売上が伸びない…」その原因と対策についてお話しさせていただきます。
ターゲット層とコンテンツのミスマッチ
「ペルソナ設定」「ターゲット層」「コンテンツマーケティング」…。コンサルタントは、こういった横文字を好んで使います。でも、要は「お客様を知り、お客様の欲しいものを提供する」という商売の基本そのものです。
昔から商店街で繁盛している八百屋さんは、お客様の好みや生活パターンを熟知しています。「〇〇さんちは、土曜の朝に必ず野菜を買い出しに来る」「△△さんは、安くても傷んでいる野菜は絶対買わない」といった具合です。
これと同じことが、実はWEBサイトでも求められています。
よく目にするのは、「若手社会人向けのサービスです」と言いながら、実際のサイトの内容は経営者向けの専門的な情報ばかり…というケースです。
これでは、せっかく若い見込み顧客がアクセスしてくださっても、「うーん、ちょっと自分には関係ない話かな」と帰ってしまうのは当然です。
コンバージョンにつながる声かけができていない
「コンバージョン率が低い」という悩みをよく聞きます。マーケティング業界では「CTA(コール・トゥ・アクション)」なんて言葉を使いますが、要は「お客様の購買意欲が最も高まったタイミングを見極めて、適切な提案をする」ことです。
ところが多くのWEBサイトでは、以下のような素っ気ないCTAに終始してしまっています。
- 「詳しくはこちら」
- 「お問い合わせはこちら」
これでは、せっかくの「商談のチャンス」を逃してしまっているようなものです。WEBサイトでも適切なタイミングで適切な「お声がけ」、つまり適切なCTAが必要になります。
効果的なCTAとは、以下のように訪問者の「いま」(滞在しているページ)に合わせた提案です。
| 滞在しているページ | CTA例 |
|---|---|
| サービス紹介ページ | 「無料相談で課題を整理しましょう」 |
| 料金ページ | 「今すぐお見積り」 |
| 事例紹介 | 「あなたの課題に最適な提案をさせてください」 |
さらに重要なのが、声かけのタイミングです。ヒートマップ分析ツールを使うと、ユーザーがどこまでスクロールしてページを読んでいるかが分かります。
「製品の特長を理解した後」「競合との比較表を見た後」など、興味が高まったタイミングでCTAを表示することで、コンバージョン率が大きく改善するケースは少なくありません。
購入につながらない訪問者しか呼び込めていない

「アクセス数が増えた!」と喜んでいたのに、売上に結びつかない。実はこれ、多くの企業が陥る”現代のWEBマーケティングの落とし穴”です。
例えば、あるBtoB企業でこんなケースがありました。情報発信サイト運営開始10カ月で月間10万PVまで伸ばしました。でも、なぜか商談数は伸び悩んでいました。
詳しくアクセス分析してみると以下の原因が分かりました。
- 人気記事は全て「〇〇の方法」「△△のコツ」系の記事
- 人気記事からサービス紹介ページへの遷移率はわずか0.1%
- 予算決定権のある経営層の閲覧はほぼゼロ
原因は明確でした。SEO対策として「検索ボリューム」だけを追いかけすぎた結果、実務担当者の情報収集需要には応えられても、意思決定者層にはまったくリーチできていなかったのです。
もちろん、情報収集需要に応えるのも重要です。しかし、重要なのは「情報収集→課題認識→解決策の比較検討→商談」と購買までの道筋をしっかり描くことです。
その上で、各段階に適したコンテンツを用意していくことで、アクセスをコンバージョンにつなげることができます。
サイトデザインの問題
「UI」「UX」という言葉もよく耳にしませんか? でも本質は「訪問者が欲しい情報にスムーズにたどり着き、ストレスなく商談や購入まで完了できる仕組み作り」です。
実店舗では「お客様の視線の動き」を意識した商品陳列をしています。お客様の目線の高さに売れ筋商品を置く。関連商品は近くに並べる。これらは当たり前のことです。
でも、不思議なことに、WEBサイトになると途端にこの基本が疎かになってしまうことが少なくありません。
たとえば、ある企業サイトのケースを紹介します。アクセス解析をしてみると、商品詳細ページまでは多くの訪問者が見てくれています。しかし、そこから先の「資料請求」や「お問い合わせ」にほとんど進んでいませんでした。
原因を調べてみると以下が分かりました。
- スマートフォンからでは資料請求フォームが画面からはみ出して入力しにくい
- 問い合わせボタンがスクロールしないと見つからない端にある
- 料金シミュレーションに必要な情報が3つのページに分散している
- 商品の詳細ページから購入ページまでに、5回もクリックが必要
こういった「見えない障壁」が、せっかくの見込み客の離脱を招いていたのです。実際、上記のケースではフォームのレイアウト改善とボタンの配置変更だけで、問い合わせ数が増加しました。
サイトアクセスを売上につなげるための効果測定と分析とは?

よく目にするのは、毎月のように代理店から届く分厚いレポートが机の隅で埃を被っているケースです。膨大なデータの中に、実は「売上を伸ばすためのヒント」が眠っているのに、それを活かしきれていない。これは本当にもったいないことです。
WEB集客で売上を上げるための効果測定がなぜ必要か?
効果測定の真の目的は「会社の利益に貢献する施策を見極めること」です。つまり、アクセス数やCVRといった表面的な指標ではなく、以下のような経営判断に直結する視点で分析していく必要があります。
- どの集客チャネルからの案件が最も粗利率が高いのか
- どんな条件の案件なら、自社のリソースを最大限活用できるのか
- どういった顧客層と組むことで、持続的な取引が見込めるのか
効果測定の本質は「無駄な投資を減らし、効果の高い施策に予算を集中させる」こと。いわば、経営者として当たり前の「投資判断」を積み重ねることです。
ある製造業で問題になった意味の薄いWEB広告
「年間3,000万円のWEB広告予算を使っています。確かにインプレッション数は増えて、クリック単価も下がっている。でも、肝心の工場の稼働率は上がっていない...」
ある製造業の経営者の言葉です。実はこれ、多くの企業が陥っている「データと経営の分断」を象徴する話です。
詳しく分析してみると以下状況が分かったそうです。
- 広告経由の新規問い合わせの80%が小ロット案件
- 広告経由案件の粗利率は平均15%低い
- 粗利率の高い大口案件は実はほとんど既存顧客の紹介
つまり、WEB施策では「売上はあるけど利益の出にくい案件」を集めることに一生懸命予算をつぎ込んでいたわけです。
「GA4の限界とは?ユーザーエクスプローラーで見えない顧客行動を深掘りする具体策」
コンバージョン率が低い原因をデータから見つけ出す方法

コンバージョン率の低下には、必ず明確な理由があります。多くの場合、以下の3つの観点から見つけ出すことができます。
- 導線
- 情報の粒度
- タイミング
ユーザーが求める情報にたどり着くまでに、不必要な遠回りを強いていることも多いです。また、専門的すぎる説明、逆に抽象的すぎる説明、どちらもコンバージョンを妨げます。
そして、いくら良い情報でも、ユーザーの検討段階に合っていなければ効果は限定的です。
ある不動産会社サイトの導線分析で見えてきたこと
ある不動産会社の例をご紹介します。マンション販売のサイトで、物件の問い合わせが伸び悩んでいました。
一般的なコンサルタントなら「デザインを改善しましょう」「写真を増やしましょう」と提案するところです。
しかし、詳細なデータ分析で見えてきた真の原因は意外なものでした。来訪者のサイト内での行動を丁寧に追跡してみると、実は「間取り図」のページで多くのユーザーが離脱していたのです。
動線上の情報粒度の改善
顧客にヒアリングしたところ、「間取り図が専門的すぎて、実際の暮らしをイメージできなかった」という声が多数でした。
この会社が取った施策は意外にもシンプルでした。間取り図に「家具レイアウト例」や「生活動線」を追加し、「リビングでくつろぐ家族の様子」「キッチンでの料理風景」といった、具体的な暮らしのイメージを提示したのです。
結果、物件詳細ページからの問い合わせ率は3倍近く上昇しました。なぜなら、「自分たちの暮らし」をより具体的にイメージできた見込み客が増えたからです。
集客データから売上に貢献しているチャネルを見極める方法
「各集客チャネルの貢献度を正しく評価する」これは口で言うほど簡単ではありません。ここで重要なのが「アトリビューション分析」と呼ばれる手法です。
アトリビューション分析3ステップ
以下の3つのステップで整理していけば、かなり明確な判断ができるようになります。
| 手順 | 洗い出す項目 | 具体的な実施方法 |
|---|---|---|
| 1:売上に繋がった案件の「逆算分析」 | 過去3カ月の成約案件について
|
|
| 2:コンバージョンまでの経路の検証 |
|
|
| 3:投資対効果の再計算 | チャネルごとに以下を算出
|
|
特に重要なのがコンバージョンまでの経路の検証
上記のなかで特に注目していただきたいのが、「2:コンバージョンまでの経路の検証」です。
多くの企業が「1:逆算分析」と「3:投資対効果の計算」には比較的力を入れています。これは、売上に直結する数字だけに、経営者の関心も自然と高くなるためでしょう。
しかし、実は最も重要な示唆が得られるのが、この「経路の検証」なのです。それは、このプロセスこそが「なぜ売上につながったのか」「なぜ離脱してしまったのか」という本質的な理由を明らかにしてくれるからです。
サイト訪問者の「行動パターン」を理解することで、より効果的な改善が可能になります。
弊社は、この「サイト内での顧客行動の可視化」を得意としています。高額なツール投資を必要とせず、効果的な分析手法をご提案できます。
実際、弊社のクライアント企業では、この「経路分析」の精緻化により、同じ集客予算で成約率を大きく改善した実績があります。まずは現状の分析方法について、お気軽にご相談ください。
KPIとKGIの設定方法実例
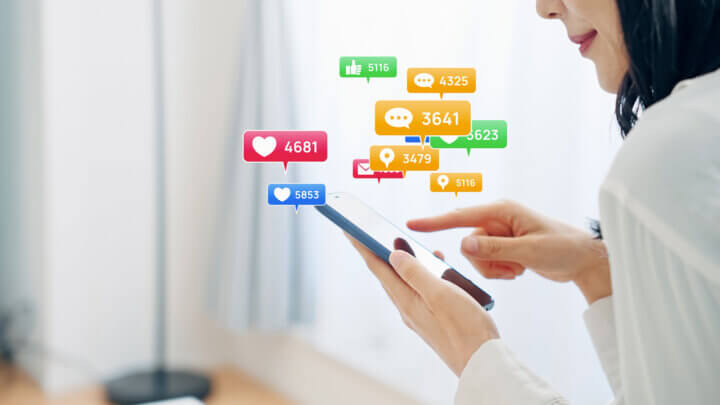
経営者である皆さんは、KPI(重要業績評価指標)とKGI(重要目標達成指標)の重要性はよくご存知でしょう。KGIは最終的に達成したい目標で、KPIは、KGIを達成するために必要な指標です。
WEBマーケティングにおいて、この設定を誤ると大きな機会損失に繋がります。
ある老舗商社でのKGI設定の失敗
あるニッチ分野での老舗商社でのケースをお話しします。当初設定していたKGIは以下でした。
- 問い合わせ数:月200件
- 資料請求数:月500件
- メルマガ会員:2000名増
一見、妥当な数字に見えます。でも、この設定には致命的な問題がありました。実は、上記は全て最終目標ではなく「中間指標」だったのです。
必要だったのは経営指標に直結するKGI
本当に必要なのは、以下に挙げるようなKGI=「経営指標に直結する数値」でした。
- 営業利益率15%以上の案件比率
- 既存顧客からの追加発注率
- 顧客の契約継続期間
この会社ではKGIを上記のように見直してデータ分析を進めた結果、以下に挙げるような驚くべき発見がありました。
- 単価の高い商材ほど、商談に進むまでの接点数が多い
- 初回の問い合わせから成約までに平均2.5カ月かかる
- 成約率の高い顧客は、必ず価格以外の相談から始まる
上記の発見から、KPIを以下のように再設定しました。
- ホワイトペーパーダウンロード後の商談化率
- メールマガジン4回以上開封者の商談率
- 業界セミナー参加者からの問い合わせ率
効果測定を通じた改善アクションの決定方法

「数字は嘘をつかない」とよく言われますが、重要なのは「どの数字を、どう解釈するか」です。
「表面的な数値の改善」に囚われることなく、本当に重要な経営指標の改善につながるアクションを見極めましょう。効果的なアクションを決定するための基本的な考え方は、以下の通りです。
ゴールを明確に設定
まず「ゴール」を明確にします。これは売上や利益といった最終的な事業目標であり、すべての施策はここに紐づいているべきです。
「PV数を増やす」という目標は、あくまでも通過点でしかありません。
ゴールと現状のギャップを把握
次に「現状とのギャップ」を把握します。ここで重要なのが「数字の関係性」です。以下に挙げるような数字の関係性を把握します。
- アクセス数は増えているのに売上が伸びない
- 問い合わせは増えているのに成約に至らない
- リピート率が低下している
これらの「ギャップ」こそが、改善すべきポイントを示唆しています。
優先順位の決定
そして「優先順位」を決定します。すべての課題に同時に取り組むことはできません。効果の大きさ、実現の容易さ、必要な投資など、複数の要素を考慮して優先順位をつけることが重要です。
改善アクションの決定
具体的な改善アクションは、以下のような流れで決定していきます。
| 改善ステップ | 具体的な決定項目 |
|---|---|
| 1:現状の詳細な分析 |
|
| 2:改善仮説の設定 |
|
| 3:具体的なアクションプランの策定 |
|
このプロセスで最も重要なのが「小さく始めて、素早く検証する」という姿勢です。完璧な施策を目指すあまり、実行が遅れてしまっては意味がありません。
まずは小規模な改善から始め、その効果を確認しながら徐々に範囲を広げましょう。このアプローチこそが、持続的な改善を可能にする王道なのです。
成果を持続して最大化するためのPDCAサイクル

多くの企業が「PDCAを回す」と言いながら、実際には「施策の繰り返し」に終始していないでしょうか。効果的なPDCAを回すために、意識すべきは以下3ポイントです。
- 適切な期間設定
- 改善の優先順位
- 仮説を持つこと
適切な期間設定
WEB施策におけるPDCAの特徴は、「スピード」と「精度」にあります。実店舗での施策と違い、すぐに効果が測定でき、迅速な軌道修正が可能です。
しかし、この「スピードの速さ」が、かえって本質的な改善を妨げることもあります。なぜなら、目の前の数字に一喜一憂するあまり、本来の目的を見失いがちだからです。
以下の異なる時間軸で目標を設定し、それぞれの期間に適した改善サイクルを回していくことが重要です。
| 期間設定 | 目安となる期間 | 注視する指標 |
|---|---|---|
| 短期 | 2週間〜1カ月 |
|
| 中期 | 3カ月〜半年 |
|
| 長期 | 半年〜1年 |
|
改善の優先順位
次に注意したいのが「改善の優先順位」です。すべての課題に同時に取り組もうとするのではなく、以下の観点で優先度を決めていきます。
- 影響度:改善による効果の大きさ
- 実現性:必要なリソースと時間
- 継続性:一時的な効果か、持続的な改善か
仮説を持つこと
何より重要なのが「仮説を持つこと」です。「とりあえずやってみる」ではなく、「なぜその施策が効果を生むと考えるのか」という明確な理由を持って初めて、効果的な検証と改善が可能になります。
フレームワークは共通だが実践方法は自社ユニークであるべき
このような改善プロセスは、一見、どの企業にも共通して適用できるように思えます。確かに、フレームワークとしての有効性は普遍的です。
しかし、ここで立ち止まって考えていただきたいことがあります。
たとえば、ECサイトと法人向けサービスサイトでは、「改善の優先順位」も「効果の測り方」も大きく異なります。ECサイトであれば、カート投入率や離脱率の改善が即座に売上に直結します。
一方、法人向けサービスでは、一見遠回りに見える信頼構築のためのコンテンツ充実が、最終的な成約率を大きく左右することもあります。
また、同じB2B企業でも、製造業と専門サービス業では、重視すべきKPIが異なってきます。製造業では生産キャパシティとの整合性が重要ですし、専門サービス業では人的リソースの最適配分がカギとなります。
つまり、「小さく始めて、素早く検証する」という原則は正しくても、その「小さく」の定義や「素早く」のスピード感は、業界特性によって大きく変わってくるのです。
弊社ではこれまで、こちらで挙げる様々な業界での改善支援を行ってきました。その経験から言えることは、成功する改善プランには必ず「その業界特有の事情」が考慮されているということです。
もし、あなたの会社の改善施策に不安や迷いがあれば、ぜひ一度、業界の実情を理解した弊社コンサルタントに相談することをお勧めします。
まとめ
「アクセスは増えているのに…」という声をよく聞きます。でも、それは決して悪いことではありません。むしろ、大きなチャンスが目の前にあるということなんです。
なぜなら、すでにあなたの商品やサービスに興味を持ってサイトを訪れている人がいる。それは、市場があなたの提供する価値を求めているという証なのです。
ただし、ここで立ち止まって考える必要があります。本当にやるべきことは「さらにアクセスを増やすこと」でしょうか? それとも、すでに興味を持ってくれている人たちの期待に、より確実に応えていくことでしょうか?
答えは明確です。まずは、現状を正確に把握することから始めましょう。過去3カ月の成約データをを専門家の視点から整理することで、次にやるべきことが見えてきます。
そして、見えてきた課題に対して、小さな一歩を踏み出しましょう。完璧な計画を立てる必要はありません。大切なのは「始めること」。そして「継続すること」。
今このページを読んでいるあなたは、すでに一歩を踏み出しています。この記事を読み終えた今こそ、次の具体的なアクションを起こすベストのタイミングです!
よくある質問
アクセス数は増えているのに売上が伸びない。今の施策を続けるべきでしょうか?
即座に現状の施策を見直すべきです。アクセス数の増加は、必ずしも質の高い見込み客の増加を意味しません。
まずは過去3カ月の実データで「どんな層からの問い合わせが実際の売上に繋がったのか」を分析することから始めましょう。このギャップを把握せずに同じ施策を続けることは、むしろ資源の無駄遣いになりかねません。データに基づいた見直しが、早期改善への近道です。
効果測定の結果、複数の課題が見つかりました。どこから手をつければいいでしょうか?
「売上への影響度」と「改善の容易さ」の2軸で優先順位をつけましょう。特に、成約に近い段階での課題(例:問い合わせフォームの完了率が低い、資料請求後の商談化率が低いなど)は、比較的少ない工数で大きな効果が期待できます。
まずはこういった「小さくても効果の見えやすい改善」から始めることで、継続的な改善サイクルを確立できます。
WEBコンサルティング会社から届くレポートの、どこに注目すべきでしょうか?
最も重視すべきは「売上に直結する指標」とその「前後の数値」です。例えば、商談化率が低い場合、その前段階(問い合わせ内容の質、対応時間など)と後段階(成約率、客単価など)の数値も併せて確認します。
単なる増減だけでなく、「なぜその数値になっているのか」という背景の理解が重要です。レポートに記載がない場合は、これらの数値の追加を依頼することをお勧めします。現場の実感との整合性を確認する上で、これらの数値は必須となります。